シティポップについて知りたくないですか?
近年、日本国内はもとより世界中で「シティポップ」が再評価され、新たな再流行現象となっています。
80年代に一世を風靡したこの音楽ジャンルが、なぜ今再び脚光を浴びているのでしょうか?
本記事では、シティポップ再流行がいつから始まったのか、その背景や特徴、そして現在の動向について詳しく解説します。
シティポップとは?ジャンルの特徴と歴史的背景
シティポップは、1970年代後半から1980年代にかけて日本で花開いた音楽ジャンルです。
バブル経済期の都市生活を背景に誕生し、ジャズ、ソウル、R&B、フュージョン、AOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)などの要素を融合させた洗練された音楽スタイルを特徴としています。
私は当時学生で、AORの代表ともいうべきアーティストの「ボビー・コールドウェル」を良く聴いていましたね。
友人は邦楽派が多数だったので、白い目で見られていましたけど・・・。
今でもこんなテイストの曲を聴き続けているので、自分の中でベースになったんだと思います。
当時の日本は高度経済成長を遂げ、都市部では新しいライフスタイルや消費文化が花開いていました。
シティポップはそんな時代の空気感を音楽で表現したものと言えますね。
洗練されたアレンジ、都会的な歌詞、そして最先端の録音技術を駆使した高品質なサウンドが特徴ですよね。
代表的なアーティストとしては、山下達郎、大貫妙子、竹内まりや、角松敏生、松原みき、杏里、佐藤博などが挙げられます。
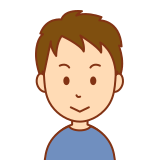
今でも第一線で活躍しているアーティストが多数ですよね!
私は年齢を重ねて感じましたが、彼らのつくる曲は『プロの曲』ということ!!
彼らの作品は当時の日本の経済的・文化的繁栄を反映した、洗練された音楽性と都会的な感性に満ちています。
1980年代末から1990年代に入ると、音楽シーンの主流はJ-POPへと移行し、シティポップは一度その影響力を失いました。
しかし、2010年代以降、この忘れられていた音楽ジャンルが再び注目を集めることになります。
シティポップ再評価の起点はいつから?再流行の始まり
現代におけるシティポップ再流行の始まりは、2010年代半ばに遡ります。
特に転機となったのは、以下のいくつかの出来事でした。
YouTubeアルゴリズムと「Plastic Love」現象
2017年頃、竹内まりやの「Plastic Love」が突如としてYouTubeのレコメンドアルゴリズムに取り上げられ、世界中の若者に拡散されるという現象が起きました。
一枚のレコードジャケット写真を使った非公式アップロードが数千万回再生を記録し、多くの海外リスナーがこの曲をきっかけにシティポップというジャンルを知ることになりました。
この現象は単なる偶然ではなく、当時のインターネット文化と深く関連していました。
ヴェイパーウェイブやフューチャーファンクといった2010年代のインターネット発の音楽ジャンルが日本の80年代音楽に影響を受けており、その文脈の中でシティポップが「再発見」されたのです。
レコードコレクターと海外DJによる掘り起こし
2010年代初頭から、海外のレコードコレクターやDJたちが日本の「obscure(知られざる)」音楽として、シティポップのレコードを収集し始めました。
Light in the Atticなどのレーベルが日本の70-80年代音楽のコンピレーションアルバムを海外でリリースしたことも、ブームの一因となりました。
特に「Pacific Breeze」シリーズや「Japanese Funk, Soul & Jazz」といったコンピレーションは、西洋のリスナーに向けてシティポップを紹介する重要な役割を果たしました。
海外では「オールディーズ」のようにシティポップを感じているんでしょうか?
私は、人種は違えど心の奥底にある感受性って同じなのかなぁ~って思いました。
ストリーミングサービスの普及
音楽ストリーミングサービスの世界的な普及も、シティポップブームを加速させました。
SpotifyやApple Musicなどのプラットフォームで、キュレーターやアルゴリズムによって作られた「Japanese City Pop」「80s Japanese AOR」といったプレイリストが人気を集め、かつてはアクセスが難しかった日本の音楽に、世界中のリスナーが容易にアクセスできるようになりました。
シティポップ再流行の特徴と心理的背景
現代のシティポップ再流行には、いくつかの興味深い特徴があります。
それは単なる音楽の再評価を超えた、文化的・心理的な側面を持っています。
ノスタルジアと「未体験の記憶」
現代のシティポップブームの中心を担っているのは、Z世代やミレニアル世代(Y世代)の若者たちです。
彼らの多くは80年代を経験していない世代ですが、そこに「懐かしさ」を感じるという興味深い現象が起きています。
これは「未体験の記憶」や「アーリーステージノスタルジア」と呼ばれる感覚に関連しています。実際に体験したことのない時代に対して抱く郷愁のような感情です。
特に不安定な現代社会において、バブル期の日本という「豊かで可能性に満ちた時代」への憧れが、この感情を強めているのではないでしょうか。
インターネット文化とレトロフューチャリズム
シティポップブームは、インターネット文化と深く結びついています。
特にヴェイパーウェイブやシンセウェイブといった、過去の未来像を再解釈するレトロフューチャリスティックな音楽ジャンルとの親和性が高いです。
80年代の日本人が描いた「未来の都市」の姿が、現代のインターネット文化の中で独特の美学として再評価されているのです。
その中でシティポップは「未来的な過去」を象徴する音楽として位置づけられています。
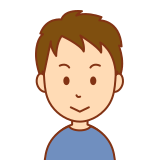
「懐かしい」と思う年代と、「新しい」と思う年代で切り口が違う両者で流行を作り上げているって不思議な感覚ですね。
グローバリゼーションと文化的交流
シティポップブームは日本国内にとどまらず、世界的な現象となっていることも特筆すべき点です。
特に韓国、台湾、タイなどのアジア諸国や、アメリカ、ヨーロッパでも熱心なファンを獲得しています。
これは音楽を通じた文化的交流の一例であり、かつては国内消費向けに作られた音楽が、インターネットとグローバリゼーションによって新たな文脈で評価されるようになった象徴的な事例と言えるでしょう。
現代におけるシティポップの影響と展開
シティポップブームは、単に過去の音楽が再評価されるだけでなく、現代の音楽シーンにも大きな影響を与えています。
新世代アーティストへの影響
現代の音楽シーンでは、シティポップの影響を受けた新世代のアーティストが増えています。
国内では、Awesome City Club、Lucky Tapes、Suchmos、Friday Night Plansなどのバンドが、シティポップの要素を現代的に再解釈した音楽を展開しています。
海外でも、韓国のCITY POPやYUKIKA、アメリカのYaeji、イギリスのMildlife、オーストラリアのTame Impalaなど、シティポップの影響を受けたアーティストが多数登場していますね。
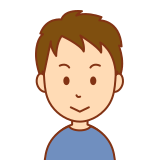
この海外のアーティストの楽曲も聴いてみてください。
意外とハマるかも?
サンプリングとリミックス文化
現代の電子音楽シーンでは、シティポップのサンプリングやリミックスが盛んに行われています。
特にNight Tempo、Desired、macross 82-99などのフューチャーファンクアーティストは、古いシティポップの曲をサンプリングし、現代的なダンスミュージックとして再構築する作品を多数発表しています。
こうした取り組みは、シティポップを新しい文脈で再解釈し、若い世代に届ける役割を果たしています。
ファッションや視覚文化への波及
シティポップのブームは音楽にとどまらず、ファッションやグラフィックデザイン、イラストなどの視覚文化にも影響を与えています。
80年代日本の広告美学やファッションが再評価され、現代のデザインやスタイルに取り入れられるようになりました。
特にSNS上では「#シティポップ」や「#citypop」というハッシュタグのもと、音楽だけでなく、ファッション、写真、イラストなどが共有され、総合的な美学として発展しています。
私も街を歩いているとダブルのジャケットを着た若者を見かけますが、まさに「シティポップ」の世界観だと感じます。
また、皆さん似合うのが悔しい~。(涙)
未来に向かうシティポップ再流行:持続か一過性か
シティポップ再流行は2020年代に入っても継続していますが、この現象は一過性のものなのか、それとも長期的な再評価の始まりなのでしょうか?
シティポップの再定義と拡張
現在のシティポップブームでは、かつての定義を超えた拡張が見られます。
もともと「シティポップ」というカテゴリは曖昧で、当時のアーティスト自身も自分の音楽をシティポップと呼んでいたわけではありませんでした。
現代では、1970-80年代の日本の都市的な音楽全般を広くシティポップとして捉える傾向があり、アイドルポップ、歌謡曲、フュージョンなど多様なジャンルが「シティポップ」というカテゴリに包含されています。
アーカイブ活動とリイシュー
シティポップブームを受けて、過去の名盤のリイシューやデジタル配信が活発化しています。
かつてはレコード店の中古棚でしか見つからなかった作品が、ストリーミングサービスで容易にアクセス可能になり、新たなリスナー層を獲得しています。
また、『パシフィック・ブリーズ』や『Japanese City Pop』などのコンピレーションが国内外でリリースされ、入門者向けのガイド的役割を果たしています。
グローバルな音楽シーンにおける位置づけ
シティポップは現在、グローバルな音楽シーンの中で「日本発の独自の音楽スタイル」として認知されるようになっています。
これはジャズやボサノヴァ、ディスコなど、特定の時代・地域から生まれながらも普遍的価値を獲得した音楽ジャンルと同様の道筋を歩んでいると言えるでしょう。
日本のポップカルチャーへの関心が高まる中、シティポップは「J-POP以前の日本の洗練された音楽」として、新たな文化的アイデンティティを形成しつつあります。
まとめ:シティポップ再流行の意義と展望
シティポップ再流行は2010年代半ばから始まり、現在も続いている音楽カルチャーの興味深い現象です。
この再流行は単なるレトロブームではなく、インターネット時代のグローバル化、文化の再文脈化、そして現代社会における「懐かしさの消費」という複雑な要素が絡み合った現象と言えるでしょう。
かつては日本国内向けに作られていた音楽が、時を経て国境を越え、新たな世代に発見され、異なる文脈で再評価されるという現象は、音楽の持つ普遍的な力と文化の循環を示しています。
シティポップはすでに「過去の音楽」という枠を超え、現代の音楽シーンに影響を与え続ける生きたジャンルへと変化しています。
今後も新たなアーティストや制作者によって再解釈され、進化し続けるでしょう。
かつて「都市」を舞台に生まれた音楽が、インターネットという新たな「都市」で再び花開いている。
それがシティポップブームの本質なのかもしれませんね。
※この記事で紹介した楽曲やアーティストは、各種音楽ストリーミングサービスやYouTubeなんかで聴くことができます。
特に「ジャパニーズ・シティ・ポップ」「80s ジャパニーズ・AOR」などのキーワードで検索すると、多くの関連コンテンツを見つけることができると思います。
最後までご覧いただきありがとうございます。
see you!



とは?メンバー構成、音楽スタイル、初心者おすすめ曲5選!-120x68.png)
コメント